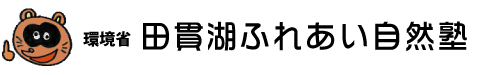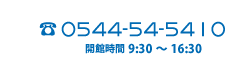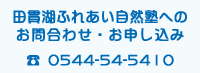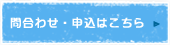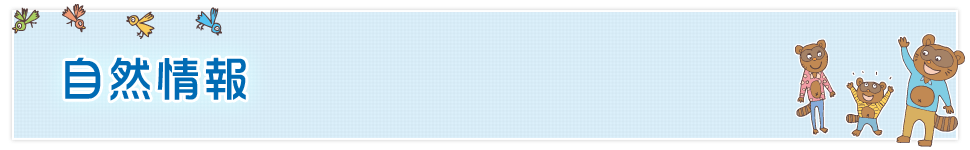
小田貫湿原
1月
温が冷え込み、湿原の枯れ草や木道に白い霜が降りて幻想的な光景が広がります。「ヒッヒッ」と響くジョウビタキの声を聞きながら、静かな木道を歩いていると、木片に小さなマッチ棒のような赤い「コアカミゴケ」が生えています。このコケはなんとも不思議な生き物で、2種類の生物が協力し合って一つの体を作り上げている「地衣類」という仲間です。植物のようでもあり、キノコのようでもあるその姿に驚かされますが、よく考えると私たちも「腸内細菌」との共生のおかげで健康に暮らしています。自然も人も、実は他の生き物と支え合って生きているんですね。そんな繋がりを感じながら、冬の散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。
【1月の生き物】
野鳥:カシラダカ、アカゲラ、カワラヒワ、エナガ、アオジ、シジュウカラ、アオジ
その他:コアカミゴケ、イノシシ(足跡、獣道)、ニホンジカ(足跡)





2月
真冬の湿原では静かな時間が流れます。朝晩の冷え込みが厳しいため木道や枯れ草には一面に霜が降り、朝日を浴びてキラキラと輝きます。木道を歩けば、湿原の枯れ草をかき分けるようにできた獣道や、地面についた足跡などが見られます。シカやイノシシ、タヌキなどが通った痕跡が、あちこちに残されているのです。足跡の形をよく観察すれば、どの動物の足跡なのかを推定することができます。ぜひ探偵になったつもりで、動物たちの痕跡を探してみましょう。
【2月の生き物】
野鳥:ホオジロ、カケス、ジョウビタキ
その他:コアカミゴケ、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ






3月
日差しが出ると、冬の厳しい寒さが少し緩みます。枯れ草の中から澄んださえずりが聞こえ、春の訪れを感じられます。ふと水溜まりを覗くと、水面にたくさんのカエルの卵が!「ヤマアカガエル」の卵です。彼らは寒さの続く早春に産卵し、再び冬眠に入ります。なぜそんなに早く卵を産むのでしょう?それは、天敵となるヘビやヤゴが現れる前に子どもを成長させ、生き残りやすくするための作戦といわれています。湿原に訪れたら、春を先取りする生き物たちの姿にも注目です。
【3月の生き物】
植物:アセビ
野鳥:ホオジロ、ジョウビタキ、カワラヒワ、シジュウカラ
その他:ヤマアカガエル、アカハライモリ、ニホンジカ、ニホンイノシシ





4月
湿原はまだ枯れ草に覆われていますが、周囲ではスミレやマメザクラが色どりを添え、春の訪れを感じます。耳を澄ませると「ホーホケキョ」とウグイスの声が聞こえてきます。ウグイスといえば、何色の鳥をイメージしますか?よく間違われるのは、鮮やかな黄緑色の「メジロ」です。名前の通り目の周りが白く、花の蜜を求めてウメやサクラなどの木を飛び回ります。実際のウグイスは枯れ草に似た控えめな色で、林や藪に隠れて暮らしています。もしかすると、現代の私たちは声の美しいウグイスと目に鮮やかなメジロを重ね合わせて、理想の春の鳥を思い描いているのかもしれませんね。
【4月の生き物】
植物:タチツボスミレ、ムラサキサギゴケ、ジロボウエンゴサク、マメザクラ、ミツバツツジ、ドウダンツツジ
野鳥:ウグイス、メジロ、ホオジロ、アオゲラ、アカゲラ、チュウヒ
その他:シュレーゲルアオガエル、ヤマアカガエル、タゴガエル






5月
湿原は鮮やかな新緑に包まれ、若葉とともに花開く「アシタカツツジ」の赤色が周囲に彩りを添えてくれます。鳥のさえずりとともにモリアオガエルの「がららら、ごろろろ」という独特な鳴き声が響き、初夏ならではの音風景を楽しむことができます。水辺では木々に産み付けられたモリアオガエルの卵塊が見られます。大切な卵を特殊な泡に包んで、外敵や乾燥から守るのです。誕生したオタマジャクシはやがて水に落ち、一か月ほどかけて小さなカエルへと成長します。世代を繋ぎ、生き物で活気づく初夏の湿原散策をお楽しみください。
【5月の生き物】
植物:アシタカツツジ、エゴノキ、マムシグサ、ウマノアシガタ、ハルザキヤマガラシ
野鳥:センダイムシクイ、ツツドリ、キビタキ
その他:モリアオガエル、シュレーゲルアオガエル






6月
梅雨のしっとりとした空気の中、早くもやってきた夏鳥たちの声を聞きながら木道の散策が楽しめます。この時期、緑の湿原に鮮やかな紫色の「ノハナショウブ」が開花します。紫色の花には、花粉をよく運ぶハチ類を呼び寄せる効果があります。花が鮮やかに咲くのは、虫に花粉を運んでもらい子孫を残すためなのです。さらに花の構造に注目すると、ノハナショウブは花に潜り込む昆虫の背に花粉がつき、運ばれた花粉をめしべが自然に受け取れる構造になっています。このように花の色や形には、様々な工夫が詰まっていることが分かります。散策をしながら、一つ一つの色や形がもつ意味を想像してみるのも楽しいですよ!
【6月の生き物】
植物:ノハナショウブ、ミズキ、ミヤマガマズミ、ハルジオン、ニワシロイチゴ、キトンイバラ
野鳥:センダイムシクイ、ノスリ、アオゲラ、メジロ、シジュウカラ
その他:シュレーゲルアオガエル、ヤマアカガエル、モリアオガエル、ギンヤンマ、カワトンボ






7月
梅雨が明けて夏の日差しが降りそそぎ、青空に草の緑が際立つ季節です。湿原の中では「ヌマトラノオ」や「チダケサシ」など湿った環境ならではの花が咲き、その上ではトンボたちが近づいたり離れたり、縄張りを競いながら飛び交います。中でも真っ赤な体の「ショウジョウトンボ」は必見です。小さな体ながら、全身が紅いオスの姿は見ごたえ抜群です。この時期、オスのトンボはメスが産卵しに来る水辺に縄張りをはって待っています。湿原に来たら、その場でしばらく観察してみましょう。子孫繁栄をかけて必死に生きる昆虫たちのドラマが繰り広げられていますよ!
【7月の生き物】
植物:チダケサシ、ヌマトラノオ、カキツバタ、クサレダマ、コオニユリ、ギボウシ、ダイコンソウ、シシウド
野鳥:センダイムシクイ、アカゲラ、ホオジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、カルガモ、
その他:キイトトンボ、ハラビロトンボ、オニヤンマ、アキアカネ、ショウジョウトンボ、シオカラトンボ






8月
田貫湖周辺でも30度を超える真夏日が続き、夏の日差しが照り付けます。湿原を歩くだけでも汗がにじむ季節です。湿原散策の際は帽子や日傘、飲み物などがあるといいでしょう。一方、小田貫湿原のの8~9月は 湿地に咲く花が多くなる季節でもあります。紫色の花が鈴なりにつくサワギキョウ、明るいオレンジ色で優雅なたずまいのコオニユリ、小さな黄色い花をたくさんつけるクサレダマなどが代表的です。湿原の緑も美しく、木道を歩くだけでも清々しい気分になります。
【8月の生き物】
植物:サワギキョウ、キセルアザミ、サワシロギク、コオニユリ、コマツナギ、ダイコンソウ、コバギボウシ、ヒメキンミズヒキ、ツリフネソウ、アサマフウロ、ワレモコウ
野鳥:ツバメ、カワラヒワ、メジロ、ホオジロ、ヤマガラ、シジュウカラ
その他:ジャコウアゲハ、マユタテアカネ、ショウジョウトンボ、ミヤマカワトンボ、クロヒカゲ、モノサシトンボ





9月
暑さが徐々に和らぎ、湿原では真夏よりも爽やかな風を感じられます。この時期「キセルアザミ」という濃いピンク色の花を見かけるようになります。この花は、下を向いた姿がタバコを吸うときに使うキセルの形に似ていることから名付けられました。なぜ下を向いているのかには諸説ありますが、足場を不安定にして訪れる虫たちに花粉がつきやすくするためだとも言われています。花期が終わるころには少しずつ上向きになり、タネを遠くへ運ぶために風を受ける準備を整えます。どんなときも最後には上を向くキセルアザミの姿は、まるで私たちに前向きな生き方をそっと教えてくれているようです。
【9月の生き物】
植物:キセルアザミ、サワシロギク、アサマフウロ、サワヒヨドリ、アキノウナギツカミ、ワレモコウ
野鳥:ツバメ、カケス、メジロ、アカゲラ、シジュウカラ
その他:エンマコオロギ、モリオカメコオロギ、ギンヤンマ、ナツアカネ、オオカマキリ





10月
朝晩の肌寒さとともに、秋の訪れを感じる季節になりました。湿原の中では、風に揺れる「ススキ」の白い穂が輝きを放ちます。ススキは秋の七草や十五夜の月見、茅ぶき屋根など、私たちにとってなじみ深い存在です。その種はふわふわの毛に包まれ、風に乗って新たな場所へと旅をします。土を選ばず、どんな環境にも根を張って育つというたくましさ。置かれた場所でしっかりと生きるその姿は、潔くてかっこよさを感じます。ススキのように、どんな場所でも前向きに根を下ろす強さを持つことも大切にしていきたいですね。
【10月の生き物】
植物:ミズヒキ、ユウガギク、タニソバ、キセルアザミ、ヤマラッキョウ、ナギナタコウジュ、ハナタデ
野鳥:ヤマガラ、シジュウカラ、カケス、ホオジロ、コゲラ
その他:エンマコオロギ、モリオカメコオロギ、アカハライモリ






11月
朝晩は霜が降りるほど冷え込みが強まり、冬が近いことを感じます。木道の周りには絨毯を敷いたかのように黄金色の湿原が広がります。その中で小さな赤い実をたくさんつける「ガマズミ」は、かつて山里の暮らしに欠かせない存在でした。果実は秋から初冬にかけて子どもたちのおやつとして親しまれ、果実酒や漬物にも利用されました。柔軟で折れにくい枝は、柴や薪を束ねる縄や道具の柄としても活躍し、その名も「鎌」「酸実」に由来すると言われています。先人たちが自然の中で見つけた知恵には、私たちが身近な自然と共に暮らす豊かさを学ぶたくさんのヒントが隠されているのです。
【11月の生き物】
植物:ユウガギク、ヤマラッキョウ、アシタカツツジ、ミヤマガマズミ(実)
野鳥:ジョウビタキ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、アカゲラ、ハシブトガラス、ヒヨドリ
その他:ジョロウグモ、フクラスズメ幼虫






12月
本格的な冬の到来です。冷たく澄んだ空気の中、木々の葉が落ちる冬は、野鳥観察にも最適な季節です。湿原の木道へ続く林の小道ではメジロやヤマガラ、シジュウカラなど複数種の小鳥が群れになる「混群」や、冬の代表的な小鳥「ジョウビタキ」の姿が見所です。混群を作る鳥たちは、仲間と協力して食べ物を見つけたり、危険を知らせあったりするために一緒に行動します。一方、ジョウビタキは冬の少ない食べ物をめぐる争いを避け、あえて群れずに一羽で過ごします。それぞれの暮らしぶりを見ていると、助け合う生き方も、一人で自分のペースを大切にする生き方も、どちらも素敵な生き方です。鳥の声が聞こえたら、立ち止まって静かに観察してみましょう。
【12月の生き物】
植物:アシタカツツジ、アセビ(つぼみ)
野鳥:ジョウビタキ、シロハラ、メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ、カケス、アオジ