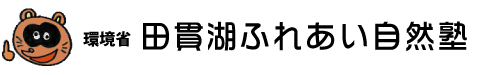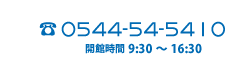自然情報– category –
-
小田貫湿原2013年5月24日
 野に咲くイチゴ! みなさんご存知、ヘビイチゴ!春先は黄色の花をつけていましたが、やっぱり赤い実は目立ちますね。 ヘビがいそうな場所によく生えているから、この名前がつきました。決して、ヘビが食べるイチゴという意味ではないんですね。 おいしそうにも見えますが、残念ながら食べてもおいしくないんです。身近な場所にも必ずある植物。 みなさん、見て楽しみましょう!(2013年5月24日)
野に咲くイチゴ! みなさんご存知、ヘビイチゴ!春先は黄色の花をつけていましたが、やっぱり赤い実は目立ちますね。 ヘビがいそうな場所によく生えているから、この名前がつきました。決して、ヘビが食べるイチゴという意味ではないんですね。 おいしそうにも見えますが、残念ながら食べてもおいしくないんです。身近な場所にも必ずある植物。 みなさん、見て楽しみましょう!(2013年5月24日) -
田貫湖畔2013年5月9日
 地を這うジシバリ! 春の黄色い花と言えば、「タンポポ」を思い浮かべる人も多いですよね。写真は「ジシバリ」という植物。 地面を這うように生育し、たくさんの花を咲かせてくれます。葉っぱも丸くて可愛らしいお花です。 この時期、少し外を歩けば沢山の黄色い花に出会えます。よーく見ていると、それぞれ形や名前が違うんですね。 その多くがキク科というタンポポの仲間達。図鑑片手に散歩に出かけてみませんか? (2013年5月9日)
地を這うジシバリ! 春の黄色い花と言えば、「タンポポ」を思い浮かべる人も多いですよね。写真は「ジシバリ」という植物。 地面を這うように生育し、たくさんの花を咲かせてくれます。葉っぱも丸くて可愛らしいお花です。 この時期、少し外を歩けば沢山の黄色い花に出会えます。よーく見ていると、それぞれ形や名前が違うんですね。 その多くがキク科というタンポポの仲間達。図鑑片手に散歩に出かけてみませんか? (2013年5月9日) -
自然塾敷地内2013年5月9日
 イロハモミジの芽吹き 3月末まで、自然塾の敷地内では大規模な工事が行われていました。その影響か、少し植物が減っている気がします。 そんな工事跡地で見つけた「イロモミジ」の芽吹き。上を見上げると可愛い花も咲かせていました。 自然の回復力は凄まじいですね。元の様子に戻るまで、何年かかるのでしょうか?しっかり見守って行きたいと思います。(2013年5月9日)
イロハモミジの芽吹き 3月末まで、自然塾の敷地内では大規模な工事が行われていました。その影響か、少し植物が減っている気がします。 そんな工事跡地で見つけた「イロモミジ」の芽吹き。上を見上げると可愛い花も咲かせていました。 自然の回復力は凄まじいですね。元の様子に戻るまで、何年かかるのでしょうか?しっかり見守って行きたいと思います。(2013年5月9日) -
小田貫湿原2013年5月9日
 分身の術! 写真は「チゴユリ」。この時期、林の中に行くとよく見られる植物です。 小さな花ですが、何年もかけて大きく成長していく努力家でもあります。 見かけるときは、かなり群生していることが多いのですが、実は分身の術を使えるんです! もちろん種でも増えるんですが、四方に根をはった先から、まるでクローンのように新しいチゴユリが生まれます。 確実に子孫を増やす工夫なんですね。人間もいつの日か、できるようになるのでしょうか・・・。 (2013年5月9日)
分身の術! 写真は「チゴユリ」。この時期、林の中に行くとよく見られる植物です。 小さな花ですが、何年もかけて大きく成長していく努力家でもあります。 見かけるときは、かなり群生していることが多いのですが、実は分身の術を使えるんです! もちろん種でも増えるんですが、四方に根をはった先から、まるでクローンのように新しいチゴユリが生まれます。 確実に子孫を増やす工夫なんですね。人間もいつの日か、できるようになるのでしょうか・・・。 (2013年5月9日) -
田貫湖畔2013年4月27日
 一見タチツボスミレかな?と思ってしまいそうですが、アケボノスミレと言います。 夜明け空のあけぼの色に例えられてこの名がつきました。 大きくてとても綺麗な色なんです。 ぜひ探してみてください。(2013年4月27日)
一見タチツボスミレかな?と思ってしまいそうですが、アケボノスミレと言います。 夜明け空のあけぼの色に例えられてこの名がつきました。 大きくてとても綺麗な色なんです。 ぜひ探してみてください。(2013年4月27日) -
自然塾敷地内2013年4月27日
 等間隔に並んで光る無数の水玉に美しくふち取りされたオシャレな葉っぱたち。 これは、なんと、朝にしか見ることができない現象なんです。 植物が夜に余分な水分を出したものと言われています。 早起きして見に行く価値ありですよー!! (2013年4月27日)
等間隔に並んで光る無数の水玉に美しくふち取りされたオシャレな葉っぱたち。 これは、なんと、朝にしか見ることができない現象なんです。 植物が夜に余分な水分を出したものと言われています。 早起きして見に行く価値ありですよー!! (2013年4月27日) -
小田貫湿原2013年4月27日
 この春、お母さんが産んだ卵から、もうおたまじゃくし達が産まれていました。 耳を澄ますと蛙の声が♪季節が変わると、鳴く蛙の種類も変わっていきます。 今聞こえるのは、 シュレーゲルガエル!! 声をたどって、ぜひ見つけてみて!!(2013年4月27日)
この春、お母さんが産んだ卵から、もうおたまじゃくし達が産まれていました。 耳を澄ますと蛙の声が♪季節が変わると、鳴く蛙の種類も変わっていきます。 今聞こえるのは、 シュレーゲルガエル!! 声をたどって、ぜひ見つけてみて!!(2013年4月27日) -
自然塾敷地内2013年4月10日
 スミレの季節 写真は「ツボスミレ」の花です。 スミレの中でも小さな花が特徴的ですが、何より白い色をしているのが目立ちますよね。 田貫湖では、タチツボスミレから始まり、フモトスミレ、エイザンスミレ、ヒメスミレなど、いろいろなスミレが顔を出してくれています。 いつも見ているスミレとなんか違うなぁ?と思ったら、お気軽に自然塾スタッフにお尋ねください!(2013年4月10日)
スミレの季節 写真は「ツボスミレ」の花です。 スミレの中でも小さな花が特徴的ですが、何より白い色をしているのが目立ちますよね。 田貫湖では、タチツボスミレから始まり、フモトスミレ、エイザンスミレ、ヒメスミレなど、いろいろなスミレが顔を出してくれています。 いつも見ているスミレとなんか違うなぁ?と思ったら、お気軽に自然塾スタッフにお尋ねください!(2013年4月10日) -
小田貫湿原2013年4月10日
 春から始める自然観察のススメ! 朱色の存在感のある花を咲かせているのは、「ミツバアケビ」です。 秋になると丸く割れた実をつけることでよく知られていますが、花の印象はあまり持っていない人も多いのでは? 名前の由来も「あくび」、「開け実」、「朱け実」など、様々言われていますが、どれも特徴的な実から来ていると考えられています。 蕾、花、実、冬芽など、よく知っている植物でも、季節を通じて見てみると、新たな発見がありますよね。 皆さんも是非、身近...
春から始める自然観察のススメ! 朱色の存在感のある花を咲かせているのは、「ミツバアケビ」です。 秋になると丸く割れた実をつけることでよく知られていますが、花の印象はあまり持っていない人も多いのでは? 名前の由来も「あくび」、「開け実」、「朱け実」など、様々言われていますが、どれも特徴的な実から来ていると考えられています。 蕾、花、実、冬芽など、よく知っている植物でも、季節を通じて見てみると、新たな発見がありますよね。 皆さんも是非、身近... -
田貫湖畔2013年4月10日
 毒草注意! 写真は「ミヤマキケマン」という花です。 湖畔を歩くと会えるこの花は、春らしい繊細な雰囲気をしています。名前の「ミヤマ」には「深山」という意味があり、山に行かないとなかなか見れない植物です。 ジロボウエンゴサク、ムラサキケマンなど似たような花を持つものもありますが、いずれもケシ科で、実は有毒の植物なんです! 「綺麗な花にはトゲがある」なんていいますが、野草を食べたりする時は十分注意してくださいね!(2013年4月10日)
毒草注意! 写真は「ミヤマキケマン」という花です。 湖畔を歩くと会えるこの花は、春らしい繊細な雰囲気をしています。名前の「ミヤマ」には「深山」という意味があり、山に行かないとなかなか見れない植物です。 ジロボウエンゴサク、ムラサキケマンなど似たような花を持つものもありますが、いずれもケシ科で、実は有毒の植物なんです! 「綺麗な花にはトゲがある」なんていいますが、野草を食べたりする時は十分注意してくださいね!(2013年4月10日)